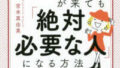🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!

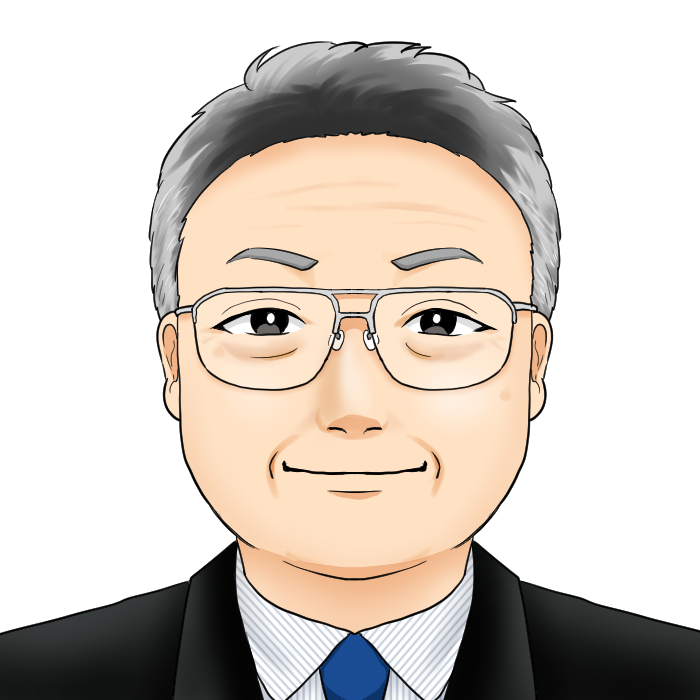
目次
1 国際関係の成り立ち
2 国家と主権
国家は、領域・国民・主権の3つの要素から成り立っています(国家の3要素)。
主権とは国の方針を決める最高権力であり、他国に干渉されない独立性を持つ権利です。
この主権を持つ国が主権国家と呼ばれます。
3 日本の領土をめぐる情勢

出典:画像 日本の領海等概念図 海上保安庁
日本の領土は,北海道,本州,四国,九州の比較的大きい4つの島と,そのほかの小さな島で構成されています。
国家の主権がおよぶ範囲(領域)は、領土、領海、領空からなり、排他的経済水域は、領海の基線から200海里(約370km)の範囲で、水産資源や鉱物資源などの天然資源の利用を沿岸国が排他的に行える水域です。
その外側が公海で、誰もが自由に利用することができます(公海自由の原則)。
周囲を海に囲まれた日本には、領土をめぐる問題があります。
北海道の択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島は、北方領土と呼ばれ、多くの日本人がこの地域に渡航するとともに、徐々にこれらの島々の統治を確立しました。
しかし、第2次大戦末期の1945年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾した後の、同年8月28日から遅くとも9月5日までの間に北方四島の全てを占領しました。
1948年までに全ての日本人を強制退去させました。今日に至るまでソ連、ロシアによる不法占拠が続いています。

出典:画像 竹島 外務省
竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
1952年以降、韓国が国際法上何ら根拠がないまま不法占拠しています。

出典:画像 尖閣諸島 外務省
尖閣諸島が、日本固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も明らかであり、現に我が国は、これを有効に支配しています。1970年代になって、中国が領有権を主張するようになりましたが、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。
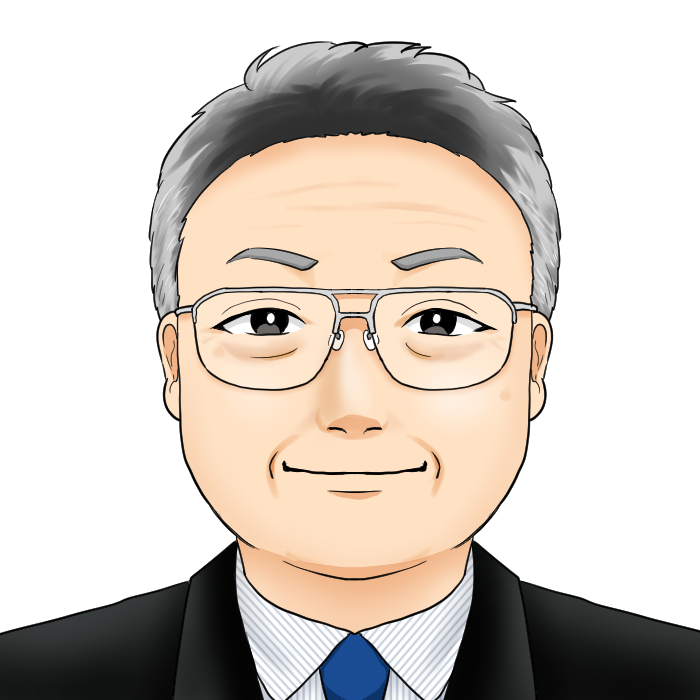
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 民族自決の原則(みんぞくじけつのげんそく)- 他国の支配を受けずに、自らの政治を自らの手で決定すべきという主張
〇 国際法(こくさいほう)- 国際社会の秩序を維持するルール
〇 主権(しゅけん)- 国の方針を決める最高権力であり、他国に干渉されない独立性を持つ権利
〇 主権国家(しゅけんこっか)- 主権を持つ国=主権・領土・国民の三要素を持った近代の国家形態
〇 領土(りょうど)- 国家が領有する陸地
〇 領海(りょうかい)- 基線(通常は海岸の低潮線)から12海里(約22.2km)までの海域
〇 領空(りょうくう)- 領土と領海の上空
〇 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)- 領海の基線から200海里(約370km)の範囲で、水産資源や鉱物資源などの天然資源の利用を沿岸国が排他的に行える水域(EEZ)
① 約4,300km²
② 約4.3万km²
③ 約43万km²
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)とは、他国の支配を受けずに、自らの政治を自らの手で決定すべきという主張。
2 (②)とは、国際社会の秩序を維持するルール。
3 (③)とは、国の方針を決める最高権力であり、他国に干渉されない独立性を持つ権利。
4 (④)とは、主権・領土・国民の三要素を持った近代の国家形態。
5 (⑤)とは、国家が領有する陸地。
6 (⑥)とは、基線(通常は海岸の低潮線)から12海里(約22.2km)までの海域。
7 (⑦)とは、領土と領海の上空。
8 (⑧)とは、領海の基線から200海里(約370km)の範囲で、水産資源や鉱物資源などの天然資源の利用を沿岸国が排他的に行える水域。
💮 答え
① 民族自決の原則(みんぞくじけつのげんそく)
② 国際法(こくさいほう)
③ 主権(しゅけん)
④ 主権国家(しゅけんこっか)
⑤ 領土(りょうど)
⑥ 領海(りょうかい)
⑦ 領空(りょうくう)
⑧ 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)
① 約4,300km²
② 約4.3万km²
③ 約43万km²
答え ① 約43万km²
1海里=1.85kmとして、
1.85×200=370 370×370×3.14=429,866(平方キロメートル)
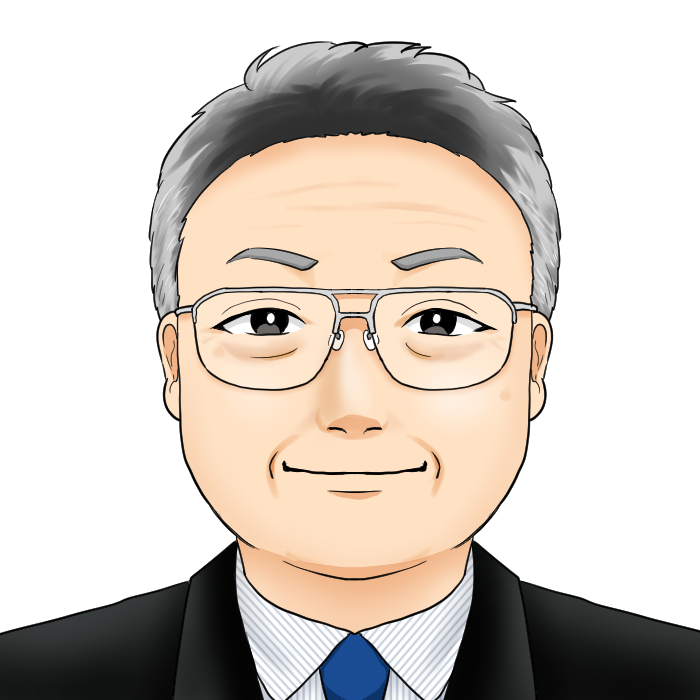
これで基礎学力バッチリですね。