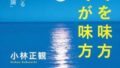🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!

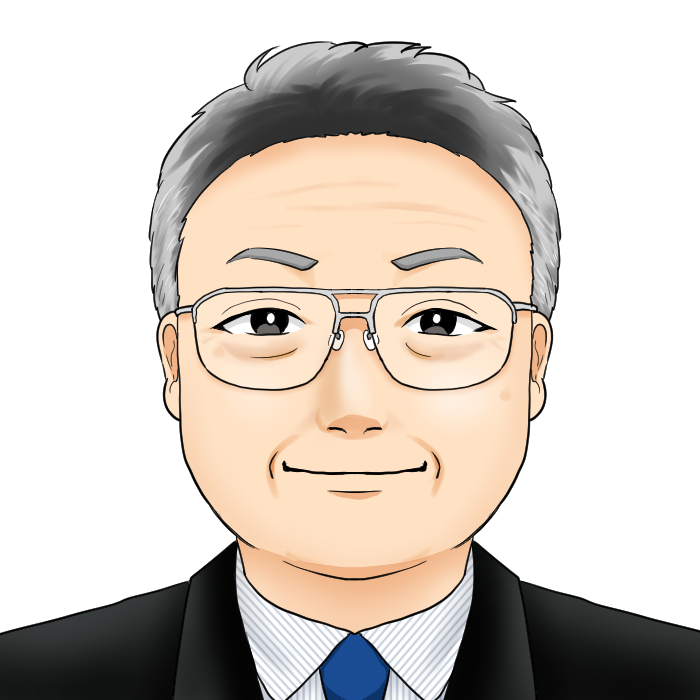
目次
1 公害の問題と改善
公害とは、環境基本法(2条3項)により、
- 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
- 相当範囲にわたる
- 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって
- 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
2 循環型社会を築く
公害対策基本法は、四大公害病の発生を受けて制定された公害対策に関する基本法でしたが、環境基本法の施行に伴い廃止されました。
環境基本法は、公害対策基本法を発展的に継承し、より広い視点から環境問題に取り組むための新しい基本法として制定され、現在の環境政策の指針となっています。
環境基本法は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とします。
環境省は、環境保全に関する行政を担当しています。
(1971(昭和46)年に環境庁が設置され、2001(平成13)年には、環境省となりました)
環境保全に貢献する社会の1つが「循環型社会」です。
循環型社会とは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念です。
循環型社会形成推進基本法では、まず製品等が廃棄物等となることを抑制し、次に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが確保されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としています。
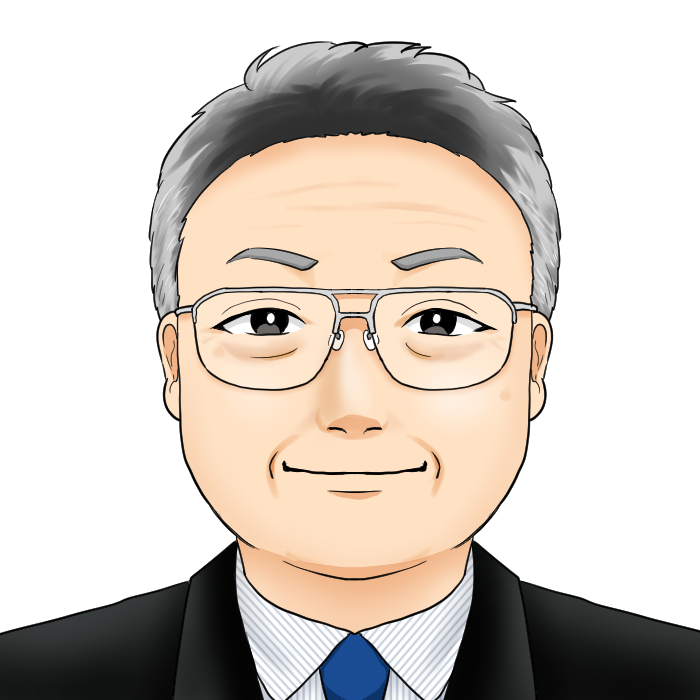
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 公害(こうがい)- 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
〇 公害対策基本法(こうがいたいさくきほんほう)- 四大公害病の発生を受けて制定された公害対策に関する基本法
〇 環境基本法(かんきょうきほんほう)- 公害対策基本法を発展的に継承し、より広い視点から環境問題に取り組むための新しい基本法として制定された
〇 環境省(かんきょうしょう)- 環境保全に関する行政を担当
〇 循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)- 天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会
◎ クイズをする ザ・水問答 環境省から
A 農業
B 日常生活
C 工業
A 約3分の1
B 約2倍
C 同じくらい
💠 7つの公害の(種類の)覚え方
7つの公害 = 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭
- 大気汚染(たいきおせん) た
- 水質汚濁(すいしつおだく) す
- 土壌汚染(どじょうおせん) と
- 騒音(そうえん) そう
- 震動(しんどう) し
- 地盤沈下(じ[ぢ]ばんちんか)ち
- 悪臭(あくしゅう) あ
覚え方は7つの公害の種類は、「た す と そう し ち あ(や)」
=「足 す と そう 7 あ」
= 大 水 土 騒 振 地 悪 = た す と そう し ち あ
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること。
2 (②)とは、四大公害病の発生を受けて制定された公害対策に関する基本法。
3 (③)とは、②を発展的に継承し、より広い視点から環境問題に取り組むための新しい基本法として制定された。
4 (④)とは、環境保全に関する行政を担当。
5 (⑤)とは、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会。
💮 答え
① 公害(こうがい)
② 公害対策基本法(こうがいたいさくきほんほう)
③ 環境基本法(かんきょうきほんほう)
④ 環境省(かんきょうしょう)
⑤ 循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)
◎ クイズをする ザ・水問答 環境省から
A 農業
B 日常生活
C 工業
A 約3分の1
B 約2倍
C 同じくらい
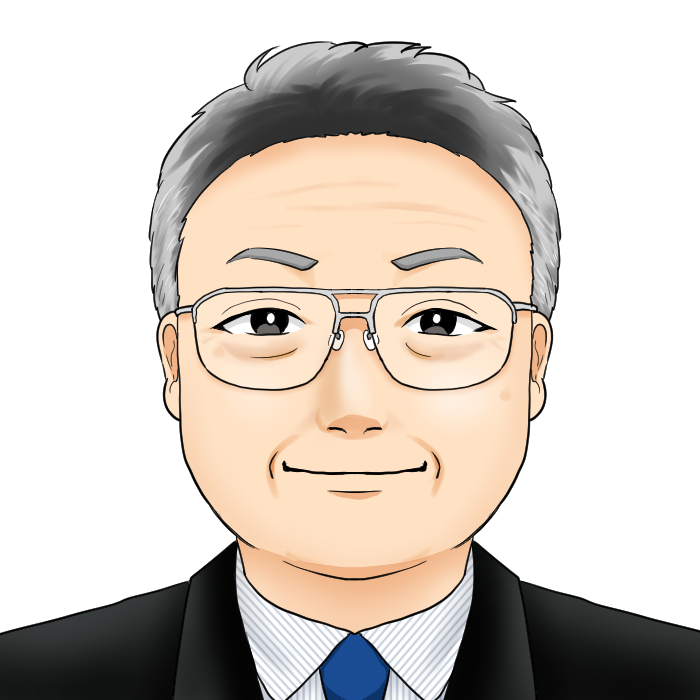
これで基礎学力バッチリですね。